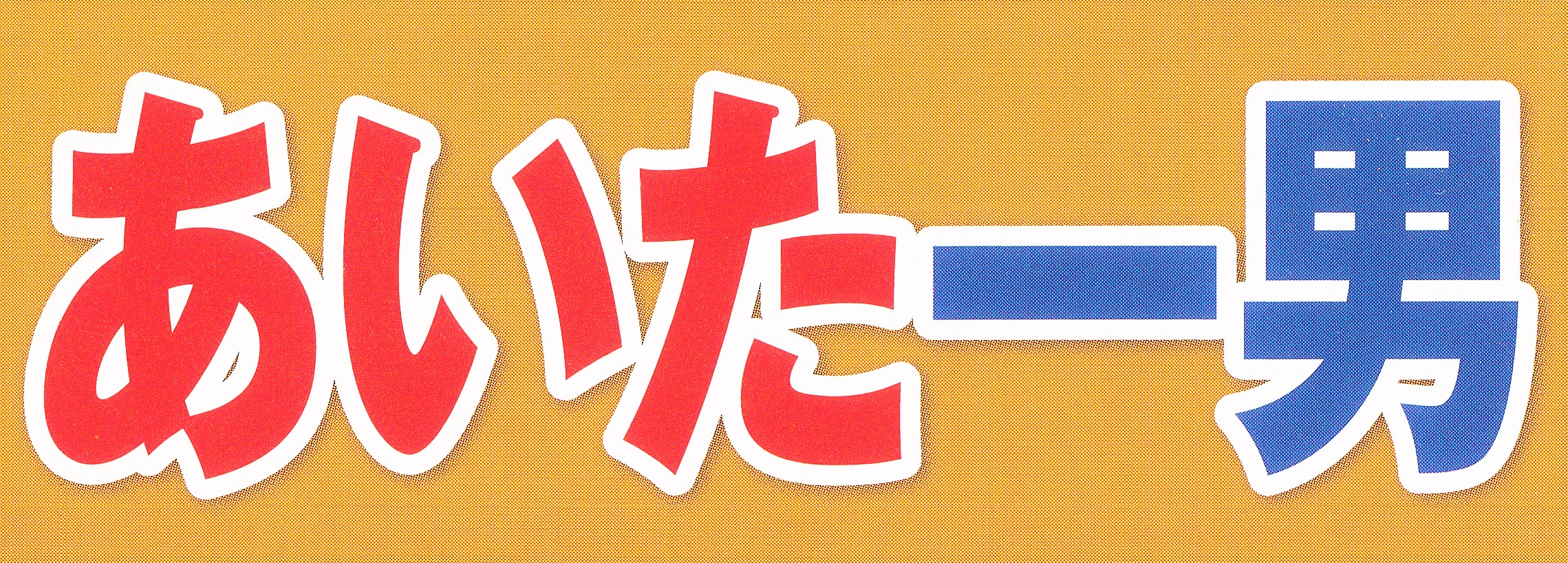定例議会にての市政一般質問
令和 6年12月 9日
次の7項目の質問をしました。
1.小中学生のタブレット端末の活用について
(1) タブレット端末を扱う際のルールについて
本市はタブレット端末を小中学生に持帰らせている。閲覧や利用時間など制限が掛けられていると思うが、扱う際のルールは?
[答弁]本市は「一人一台タブレット端末管理・運用の手引き」を全ての市立学校に配布し共有を図っている。SNSやチャット機能が使用できなく設定し、小学生は午後9時以降、中学生は午後11時以降のインターネト接続を制限している。健康面や個人情報についても指導を行っている。
(2) タブレット端末の活用状況について
日本の子ども達のタブレット端末使用状況はゲームや動画視聴などの使い方が多く、学習に関係した使用頻度が極めて低い。本市ではどのような活用状況にあるのか?
[答弁]ゲームや動画視聴についてフィルタリングを設定し制限しているが、あくまで学習を目的として貸与されていることを児童生徒に理解させながら「日常の学習ツール」として活用できるよう支援していく。
2.学校とPTAについて
PTAの参加義務を撤廃する小学校があり、PTAのあり方の見直しが行われている。
(1) PTAの見直しと学校の負担について
PTA委員会の見直し等で学校側の負担が大きくなっている事例はないのか?
[答弁]文部科学省が作成した「PTA活動実践事例集」においてPTA組織のスリム化や活動の見直しがされており、本市においても各学校の実態に応じて見直しを図っている。このような取組みから保護者と教職員の負担軽減につながっている。
(2) 廃品回収の廃止に伴う影響について
手間が大変と廃品回収をやめたPTAがあるが、これらの収益は部活動などへの補助として役立っていると思うが、やめたことで部活動への影響は?
[答弁]各PTAにおける廃品回収を廃止したことで保護者負担の増加や部活動への影響があったとの報告は受けていない。
(3) 学校と地域の繋がりについて
地域との繋がりが希薄化しており、方部委員会を廃止したPTAもあり、今後学校と地域との繋がりをどのように維持していくのか?
[答弁]本市は中学校区において49の学校運営協議会を設置の上、本市教育委員会が市立学校全76校を「コミュニティ・スクール」として指定し、地域の皆様に協議会委員として参画いただいている。今後も地域学校協働活動と一体的に推進しながら学校と地域との更なる連携を図っていく。
3.オンライン診療について
(1) オンライン診療を行っている医療機関数について
本市においてオンライン診療ができる医療機関は多いと思うが、その数は?
[答弁]オンライン診療を行う医療機関は東北厚生局へ保険診療に係る施設基準等の届出が必要で 2024年10月1日現在で34の医療機関がある。
(2) オンライン診療の実態について
本市においてオンライン診療が具体的にどのように行われているのか?
[答弁]本市の各医療機関においては医師の判断にて実施しており、報告を求める規定が無いため 具体的な実態は把握していない。
(3) オンライン診療の推進について
大病院では受付から支払・薬局など多くの時間を要する。このためにも医療機関の協力を得てオンライン診療が可能な診療科目から始められるよう本市がリードしていくべきでは?
[答弁]本市のオンライン診療の推進は医療機関から要望等があった場合は郡山医師会などの関係機関と連携し適切に対応していく。
4.有害鳥獣の駆除と猟友会の協力について
北海道でヒグマ駆除に際し、駆除にあたった猟友会が問いただされている。本市でもツキノワグマやインシシが生息しており駆除には猟友会の協力が不可欠である。駆除に協力した方が、緊急避難として行動した場合に法的責任が問われるのはおかしいと思うが猟友会との協力のありかたは?
[答弁]本市は「鳥獣保護管理法」に基づき福島県猟友会郡山支部に協力を頂いているが、クマ、インシシ等の出没多発を受け、同法の見直し・改正され次第、新たな体制の構築を実施する。
5.防災力の向上に向けた町内会加入の促進について
以前に本市の水害で町内会未加入の方が、避難情報等が伝わらず亡くなられた事例がある。市として防災力向上のためにも町内会への加入促進を更に進めるべきでは?
[答弁]2024年6月1日現在の町内会加入率は60.6%で減少傾向が続いている。町内会は安否確認、 避難誘導等に大きな力を発揮し、防災力のために町内会の必要性を強く実感する。今後は町内会の皆様とノウハウや知見を共有し、協働による町内会加入率の向上に取組んでいく。
6.組織改編について
2025年4月1日からの行政組織改編案が示された。組織改編の3つの理念として
① 「SDGs未来都市計画」、「郡山まちづくり基本方針」の着実な推進と「新時代100年創造都市実現型」課題発見・解決先進都市の創生の実現。
② 2030年・2040年・2050年からのバックキャスト思考で時代の変化に即応できる組織体制構築。
③ 部局間連携・部局間協奏により縦割りを打破し「ウェルビーイングなまち郡山」の実現、及び市民サービスの向上を可能とする組織体制の構築を目指す。
とあるが、言葉等わかりづらい。農林部と産業観光部の統合に関しても農業都市郡山の農業を軽視しているとの声も聞く。特にJAを始めとする農業団体にも説明されたと思うが今回の組織改編は農業の軽視につながらないのか?
[答弁]農商工においては「農商工等連携促進法」や「六次産業化・地産地消法」の施行、「食料・農業・農村基本法」の大幅改正などの農業動向により本市はより成長力のある農業を目指して適応力のある組織づくりを検討した。農業は将来にわたり本市の発展を支える重要な産業と認識しており、農業をはじめとした産業全体のSDGsの理念による更なる発展を目指す方針とした。
7.孤独・孤立対策について
福島県は市町村、社会福祉協議会、各種NPO団体などの関係機関と連携し、孤独・孤立対策と支援に一体的にあたる体制を今年度中に構築するとあるが、支援するにあたって行き過ぎた個人情報の保護が弊害となっていないか?又、支援に支障がある課題を把握し解決する場として地域協議会の設置が予定されていると思うが、どのような役割を担うのか?
[答弁]孤独・孤立の問題は新型コロナウイルスの影響により一層深刻な問題になっている。又今後単身世帯の増加等により更なる深刻化となる。政府は「孤独・孤立対策推進法」が2024年4月1日に施行された。地域協議会は設置が地方公共団体の努力義務とされており、今後の推進については関係部局と相談し地域協議会が真の目的を達成できるよう努力していく。